
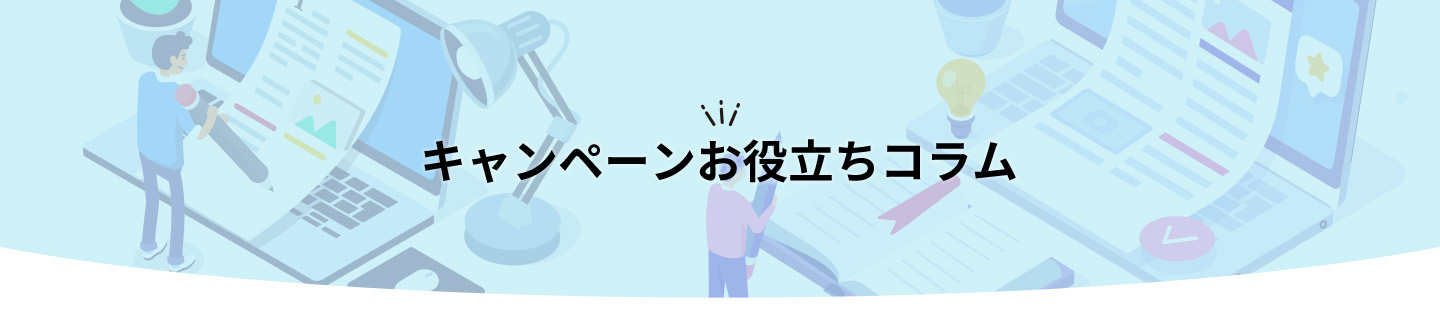
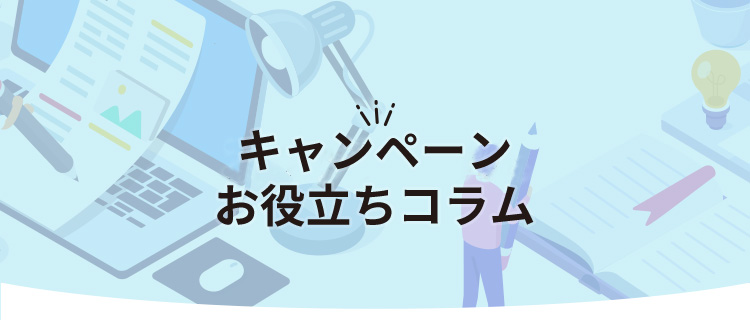
投稿日:2025-09-30
更新日:2025-09-30

(この記事は約7分で読めます)
「え、キャラクターが机の上に!?」
忘れもしません。筆者の初めてのAR体験は幼少期、某3D機能のあるゲーム機に付属していたARのカードでした。まだARが世に知られていない頃、勉強机の上に某有名キャラクターが現れたあの光景は、ただの“遊び”を超えて、記憶に残る“体験”になりました。
あれから10数年が経過した現在、AR技術は広く知れ渡り、販促・プロモーションの武器になりつつあります。“体験”として記憶の中に刻むことができるARを利用した販促方法。今回は、拡がりを見せるARについてのご紹介と、今話題の推し活にピッタリなARピクステッカーをご紹介いたします。
【この記事で分かること】
★ARについて、コストを抑えつつ導入する方法
★推し活とARを組み合わせた事例
★ARピクステッカーを使ったキャンペーン例
目次
AR(Augmented Reality/拡張現実)とは、現実世界にデジタル情報を重ねることで、視覚・空間認識に新たな層を加える技術。例えばスマートフォン(以下、スマホと表記)やタブレット等をかざすと、画面上にキャラクターが浮かび上がる・動き出すなど、現実を“拡張”しコンテンツを楽しむことができます。現実に仮想情報が付与されることで、幅広い演出・体験をユーザーに提供できるのが大きな特徴です。
近年では、眼鏡型で装着して楽しめる、「スマートグラス(ARグラス)」といった専用の端末も。また、実寸大のデジタル家具を画面上に映すことで試し置きできるなど、販促ツールとしてもARは活用されています。
ARの歴史は意外と古く、今から1世紀以上も前にさかのぼります。
1901年に発表されたSF小説『The Master Key:An Dlectrical Fairy Tale』(『ザ マスター キー』)※の中で、眼鏡をかけると人の性格が見えるという設定が登場しています。
※『The Master Key:An Dlectrical Fairy Tale』・・・ライマン・フランク・ボーム著
1968年には、コンピューター科学者アイヴァン・サザランドが世界初のヘッドマウントディスプレイを開発。1990年代には軍事・医療分野での応用が始まり、2000年代にはスマートフォンの普及とともに一般向けのARアプリが登場しました。
そして、ARが“体験”として広く認知されたのは、2016年にNianticがリリースしたアプリ・『Pokemon GO』※です。スマホを通じて、誰でも簡単にAR体験ができ、AR技術の魅力が世間一般に広まりました。
※Pokemon GO(ポケモンGO)・・・アプリのAR機能で、ユーザーが現実の街中を歩きながら、デバイス上に現れるポケモンを集めていくゲーム。世界中で数億人がダウンロードし社会現象となった。
このように、ARは“空想”から“体験”へと進化し、今では販促の武器として活用できるフェーズに入っています。
ARとよく似た言葉に「VR」という言葉があります。
VR(Virtual Reality/仮想現実)とは、コンピューター技術によって作り出された仮想空間に、ユーザーが没入して体験できる技術。専用のゴーグル型デバイス(VRヘッドセット)を装着することで、視覚・聴覚・時には触覚まで含めた“まるでその場にいるかのような臨場感”を得られます。また、不動産業界で、複数人が同時に参加できるVRモデルルームを提供し、内見さながらの体験をする事例や医療研修用として、急患の対処法・手術方法を、臨場感を保ちながら学ぶ事例もあります。
つまり、ARは現実世界を補完・拡張するのに対し、VRは現実を遮断し、仮想空間に没入するという違いがあります。
ARとVRの違いは以下の通りです。
| AR(拡張現実) | VR(仮想現実) | |
| 表示環境 | 現実世界+デジタル情報 | 仮想空間 |
| デバイス | スマホ、タブレット、ARグラスなど | VRヘッドセット |
| 体験の性質 | 現実を補完・拡張する | 現実を遮断し、仮想空間に没入する |
| 主な活用事例 | 小売・マーケティング・製造・観光 | 研修・教育・医療・不動産・イベント |

現実世界を拡張するARと仮想空間に没入するVR。
販促やキャンペーンでは、手軽に体験できるARの方が活用しやすい傾向があります。用途に合わせそれぞれの特徴を活かすことで、ユーザーの記憶に残る“体験”が提供できるのではないでしょうか。
AR体験には、主に2つの提供方法があります。1つは従来のアプリAR、もう1つが近年注目されているWebAR(ウェブAR)です。
ブラウザARとも呼ばれるWebARとは、ブラウザ上で体験できるARのことで、スマホやタブレットでQRコードを読み込むだけでAR体験ができます。つまり、専用アプリのインストールが不要で、Webサイトにアクセス後、そのままARを体験できるのが大きな特徴です。
従来のAR体験は、専用のアプリをインストールする必要がありました。しかし、アプリのインストールには、ユーザーにとって手間や時間を取るといった、利用までのハードルが生じます。そんなアプリよりも開発費用を抑えられる上、Webブラウザがあれば使える手軽さから、近年では多くの企業や自治体で導入されています。
WebARとARアプリの違いは以下の通りです。
| WebAR | ARアプリ | |
| コスト | 比較的少ない工数 低コストで開発可能 | 機能が豊富 比較的開発コストが高い |
| 拡散性・ユーザーリーチ | ・SNSマーケティングとの相性が良い ・アプリのインストール不要のため、潜在的なユーザーリーチが大きい | ・アプリからのシェアになるため、 ダウンロードが必須 ・リーチが限定的になる可能性 |
| 機能面 | 機能制限あり、ARアプリに比べて動作の精度が劣る | 高機能、滑らか操作が可能 |
| メリット | ・アプリのインストールが不要 ・即時性が高い | ・イメージにより近いAR体験を 実現可能 ・アプリをダウンロードすれば、いつでも体験できる |
| デメリット | ・ARアプリほど機能が充実していない ・QRコードやURLが分からなければ、AR体験ができない | ・アプリのインストールが必要 ・高機能な分、古い端末やアプリのバージョンによっては動作しない ことがある |
| 向いている用途 | ・より多くの人に利用させたい場合 ・期間限定の企画、拡散してもらいたい場合 | ・情報量が多く複雑なコンテンツ ・継続して利用してもらいたい場合 |
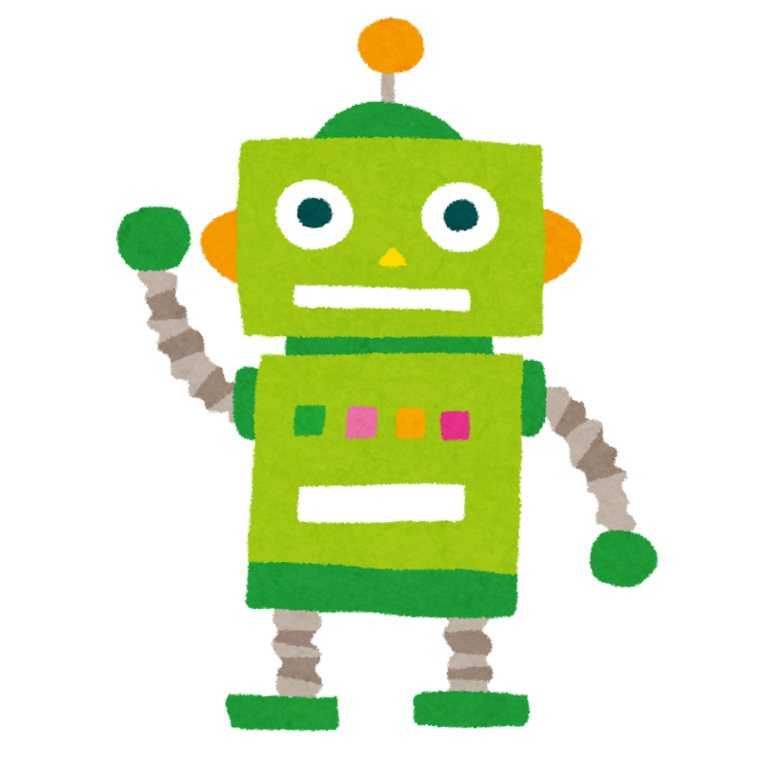
WebARは「入口としての体験」に!
アプリARは「深いブランド体験」に!
あなたには「推し」がいますか?
特定のキャラクター(=二次元)やアイドル、スポーツチーム(=三次元)等を応援する活動=「推し活」。グッズを購入したり、ライブ・イベントに参加したり、SNSで“好き”を発信したり……。その活動内容は、多岐にわたります。「推し活」はスマホ・SNS・サブスクリプションの普及、コロナ禍における自粛生活に伴い一般化し、2021年には新語・流行語大賞にもノミネートされました。市場規模は今や約3.5兆円規模とも言われ、推しとファンとの“距離感”を縮める施策が求められています。
AR(WebAR)はそんな推し活にピッタリの技術。“推しが目の前に現れる”という体験は、ファンにとって忘れられない記憶になります。
アニメやアイドルのグッズにQRコードを付けることで、ファンがそのグッズをスマホでスキャンしAR体験を楽しむことができます。例えば、推しキャラやアイドルの3Dモデルが現れたり、専用のメッセージが流れたりするなど、ファンはグッズを通じて推しとの距離がグッと縮まったような感覚を味わえます。
アーティストやグループのライブ・イベントで、観客が専用アプリを使ってARコンテンツを楽しむ事例も増えています。
アニメやゲームのイベントで、WebARを使ったプロモーションを行うケースもあります。ファンが特定の店舗・場所に行き、スマホをかざすことで、キャラクターが現れる仕組みです。ファンがその体験をSNSでシェアすることで、拡散を促す効果も狙うことが可能です。
そして、こうした”体験価値”を手軽に提供できるのが、私たちがご提案する「ARピクステッカー」です。
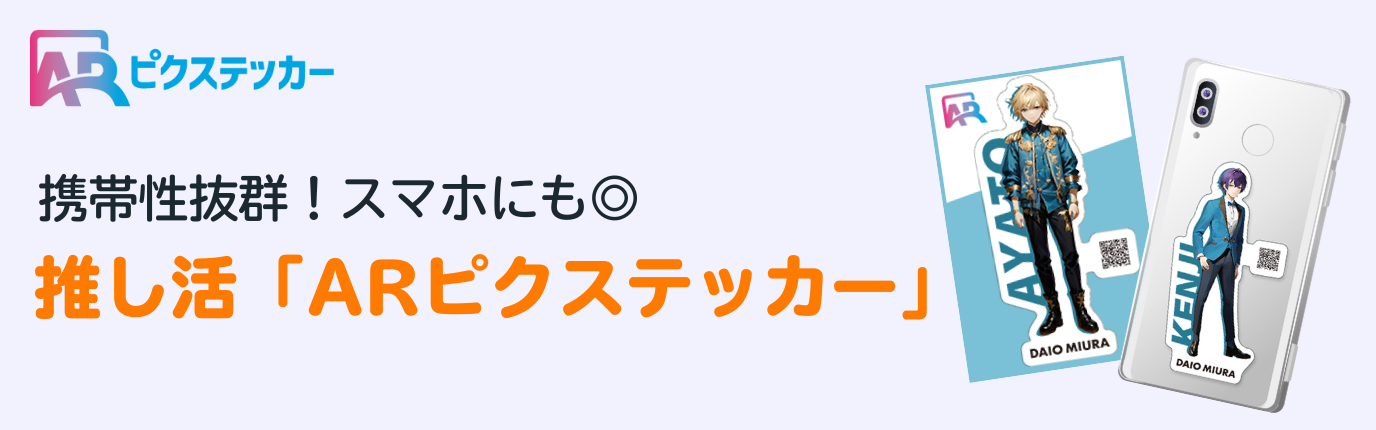
ダイオーミウラでは、ARピクステッカーで推し活をサポート!
ARピクステッカーは、印刷物にQRコードを組み込み、WebARでキャラクターやメッセージを表示できるステッカーです。

さらに、ARピクステッカーと組み合わせたこんなキャンペーンもご提案。
①SNS写真投稿キャンペーン
ARピクステッカーを使って写真を撮り、SNSに投稿。
投稿者の中から抽選で豪華プレゼントが当たるキャンペーン。
楽しさも話題性も獲得できる参加型の企画で、認知拡大施策に最適です。
②フォトコンテスト
ARピクステッカーを使った写真を、ハッシュタグを付けてSNSに投稿。
厳正な審査で優秀作品を選定し、景品をプレゼントするキャンペーン。
優秀作品は公式WEBサイトやSNSに掲載し、ブランドイメージを構築します。
③ファン向けプロモーション
機能を追加したピクステッカーで、エンタメ作品の話題性を高め、販促効果アップ。
キャラクターや世界観を活かした演出で、SNS上で拡散。
ファンとの関係強化や“バズり”のきっかけづくりに貢献します。
当社はLPの制作やキャンペーン事務局代行、景品の選定・発送など、キャンペーンに関わる業務を一括で承っております! もちろん、お客様のご要望に合わせたキャンペーンのご提案も行います。
推し活×ARピクステッカーで、新たな“体験”を!
AR×キャンペーンで、効果的な“販促”を!
ARは、単なる技術ではなく記憶に残る“体験”を生み出す手段です。
机上で筆者の推しがジャンプしてから10数年。WebARの登場により、その体験は簡単に・すぐに届けられるものへと進化しました。そして、「ARピクステッカー」は印刷物という“販促の原点”に“デジタル体験”を融合させるツールです。次のキャンペーン企画では、ぜひARピクステッカーを取り入れてみてはいかがでしょうか。
ステッカーがARで動いたり喋ったりすることで、「推し活」がより特別で楽しい体験に変わる
映える独自のユーザー体験となるため、シェアされる可能性があり、キャンペーンやイベントの認知に期待できる
スマホだけで体験可能、特別な機材不要。既存のノベルティをベースにして付加価値をプラスできる
AR×キャンペーンは、ダイオーミウラにご相談ください。
安心のサポート体制でキャンペーンの成功をお手伝いします。
ARピクステッカーのサンプルご希望もお気軽に問い合わせください!
※サンプルには数に限りがございます。予めご了承ください。
ご相談・お問い合わせはこちらのボタンから
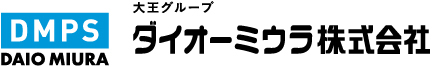
©ダイオーミウラ株式会社 2023